The Legal Mind Education Of Japan
理事長からのお知らせmessage
「木谷先生を偲んで」
木谷先生は、冤罪問題の根底には、国民の意識と教育の課題があるとお考えでした。行動には何らかの理由があるので、どんな立場に立っても、他者の話をよく聞いて、理解しようとする態度がとても大切であると、いつも話していらっしゃいました。
「法育」という言葉を作り、論理的主体性の重要性についてご理解いただきたいという思いから、2016年「日本法育学会」として活動を始めました。第1回の研究大会の特別講演では、木谷先生は「冤罪と教育」という演題でご講演下さいました。
先生にお願いに伺った時のことは、今でも忘れられません。冤罪を教育の視点からお話いただけませんか、とお願いしたところ、その意図を直ちに理解され、ご快諾されたのです。
その後、刑法学会でお会いするたびにお声かけいただき、並んで歩いた駅までの帰り道、たくさんのことを学ばせていただきました。
木谷先生のお考えと私どもの会の目的に共通点があることは、冊子(日本法育研究第1号)をご覧いただければ、ご理解いただけると思います。
この小さな学会に、先生が温かいまなざしを向けて下さったことに心から感謝し、これからも研究と教育活動を続けて参りますことをお約束して、お礼とお悔やみの言葉といたします。
日本法育学会理事長
平野 節子
「中学生と裁判傍聴」
8月1日、東京地方裁判所にて中学生40人と傍聴しました。
冒頭陳述から判決まで90分の公判で、裁判手続がよくわかった裁判でした。
令和6年5月、被害者が自転車で横断歩道を渡っていたところ、最高時速40キロの道路を時速約60キロで走ってきた前方不注意のトラックに跳ね飛ばされ、脳挫傷、顔面骨折、肋骨骨折等で90日間の入院を余儀なくされた、過失運転致傷事件でした。
加害者は長年トラック運転手をしていました。事故を起こしたことに反省はしているものの、運転にはリスクがつきものだし、制限速度を守るより、車の流れにのる方が大事だと主張し、裁判官が詰め寄る場面もありました。
傍聴に来ていた被害者が、中学生に話しかけてきて、被害の状況など詳しく知ることができたことは、子どもたちにとって、事故の怖さについての印象深めたと思います。
判決は、懲役1年2月、執行猶予3年でした。
裁判傍聴は、国民の権利です。マナーを守れば、自由に傍聴できます。
裁判の流れや事件についての詳しい解説をお聞きになりたい場合は、日本法育学会事務局までご連絡下さい。
日本法育学会理事長
平野 節子
「水俣病の加害者と被害者」
日本法育学会理事長
平野 節子
令和6年10月14日、日本法育学会と鹿児島大学、志學館大学の合同研究大会が鹿児島の志學館大学にて行われました。その前日、水俣病の現地研修を行いました。そこで学んだことの一端をお知らせしたいと思います。
1,水俣病発生の地
水俣病により多くの人々が苦しむ地は、熊本県の最南部で、八代海(不知火海)に面した漁業を主な産業とする地域です。地引網や巾着網、打瀬網などの漁法でイワシを中心に漁を営む人々や海水から塩を生産して生計を立ててきた人々が住んでいます。八代海は漁業資源がとても豊富で、地域の人はほぼ毎日、魚介類を食べて暮らしていました。
ところが、1954年のある日から、地域の猫が踊っていたかと思うとバタバタと死んでいくのです。そのうち、水俣の人々にも全身の痙攣がはじまり、指先の感覚が鈍くなり熱いものを触ってもわからない、匂いがわからない、目がよく見えない、まっすぐ歩けないなどの症状が現れ始めました。1956年にチッソ附属病院の細川一医師が「今までに見たことがない患者」として水俣保健所に届出をしたことで、調査が始まりました。
「奇病」だ「伝染病」だと恐れられ差別され、当時は、うつる病、遺伝する病と思われたために、結婚の機会も奪われました。被害者は、健康が奪われただけでなく、社会的・経済的にも追いつめられていきました。
2,原因がわかっても
調査の結果、チッソ水俣工場の排水に含まれるアセトアルデヒド等の化学物質製造過程で排出されるメチル水銀を含む工場排水が原因であることがわかりました。百間水門を通して大量の有害排水が海に流され、人々は汚染された魚介類を長期間・大量に食べたことによって引き起こされた健康被害や環境汚染です。
1965年の新潟第2水俣病が発見され訴訟が起こされたことにより、1967年には「公害対策基本法」が制定され、1968年に厚生省は、水俣の奇病の原因はチッソ工場の排水であると発表し、「公害」と認定します
チッソは、政府の庇護を受けて「日本窒素肥料株式会社」として1906年に発電会社から転換し、水俣に化学肥料製造工場を設立しました。化学肥料で莫大な富を得たチッソは、総合化学企業として、日用品から工業品、軍需品まで製造し、世界に名をとどろかせました
主なチッソ製品は、現在も皆様の身近にあります。化学繊維(ベンベルグ、アセテート等)、油脂(グリセリン、人造バター、大豆油、石鹸等)、工業製品(アンモニア、無水酢酸、カーバイト、硫酸、苛性ソーダ、化学調味料、さらし粉等)、火薬(硫安ダイナマイト、電気雷管、黒色鉱山火薬等)は、高度経済成長時代には生活に必要不可欠になっていて、すでに体内に多く取り込まれている物質が多いことに驚きました。
チッソ水俣工場では、合成酢酸の原料であるアセトアルデヒドや塩化ビニルを作るための触媒に水銀が用いられ、その過程で水銀が有機化してメチル水銀が副生されます。メチル化すると、タンパク質と結合しやすくなるので、飛躍的に毒性が増すそうです。そうして製造されたグルタミン酸ソーダ、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレンなどは、現在も生活の中に溢れています。ラップ、タッパー、衣料品、接着剤、医薬品や塗料など、数え切れないほど多様な種類です。製品から有害物質は溶け出して利用者に被害はないのか疑問になりますね。工業発展の陰で、その調査はなおざり(隠ぺい?)にされてきました。ようやくプラスティック製品から有害物質「環境ホルモン(内分泌かく乱物質)」が溶け出していると知られるようになってきたところです。
3,水俣病の補償
政府やチッソは、水俣病の被害者に金銭的補償をしています。しかし、それによって被害者の生活が楽になった、安心したと手放しで喜べる状況にはなっていません。補償はどの程度の症状の者が受けられるのか、数年後後発的に症状が出た場合にも補償されるのか、子孫への補償はあるのかなど、その線引きが難しく、受けられる人と受けられない人との分断が深まっているそうです。60年を経た今でも、未だ差別と偏見はなくならず、水俣で育ったことを明かせない、以前に患者であったことを隠す人もいます。水俣病の被害は、今も終わっていないのです。
4,水俣の現在
(1)百間水門
チッソが工場を稼働するまで、百間水門は塩作りのために海から海水を取り入れる水門でした。満ち潮で海水を溜め、海水を塩田にまき、蒸発させ、ある程度濃縮させてから大鍋で煮詰めて塩を取り出すのです。水俣では、古代からこの方法で塩を作っていました。
ところが、チッソ水俣工場ができたことで、ここは、汚染された工業廃水を海に流す水門になってしまったのです。1932年から水俣病が政府に認定される1968年までメチル水銀を含む有害物質を八代海一帯に流し続けたのです。
市は、百間水門を「水俣病の原点」と紹介しているのにも拘わらず、安全面を理由に水門を撤去することを決めました。水俣病を後世に伝える証拠である遺構を消し去ろうとしている市に対して「水俣病胎児性・小児性患者・支援の会」の方が水門の前で必死に説明していました。
(2)行政の取り組み
国や熊本県、水俣市は、水俣市明神町に、国立水俣病総合研究センター、熊本県環境センター、水俣市立水俣病資料館を同地に設立し、水俣病の歴史や紹介の展示をしています。概要をつかむのには良い施設です。周辺には、エコパーク水俣という広大な運動場や公園があるのですが、そこは、水俣湾の水銀を含むヘドロを埋め立てて造られた41.4haの埋め立て地です。水俣湾のヘドロは、道路造成にも使われたと地元の人から聞きました。
(3)水俣病歴史公証館
小高い山の上に、30年以上水俣病患者を支援し、収集・検証した資料や実物を展示している民間の資料館があります。ボランティア職員の方が、丁寧に説明をして下さり、包み隠さずどんな疑問にも答えてくれます。患者の方々の苦しみが肌で感じられ、胸が痛くなりました。当日は、ユネスコの職員の方々も隣の小屋に宿泊して見学していました。
5,現場を知る大切さ
水俣病は終わったことではなく、その加害者は、「便利さ」ばかりを求める私たちなのだということを思い知らされます。3R(リユース・リデュース・リサイクル)など、できることから取り組まなければと思いました
当日は、熊本の方にご案内いただき、土地ならではの課題もお聞きすることができました。報道されていない被害者の真の苦しみや地域の現状は、現地に足を運ばないと知ることはできないと強く思いました。
水俣病は、イタイイタイ病、四日市ぜんそく、新潟水俣病とともに、四大公害病と小学校では教えます。しかし、自ら進んで知ろうとしない限り、その真実と実態を知る機会はほとんどないのが現実です。
是非、皆様も水俣へお出かけください。
「日本法育学会のめざすもの」
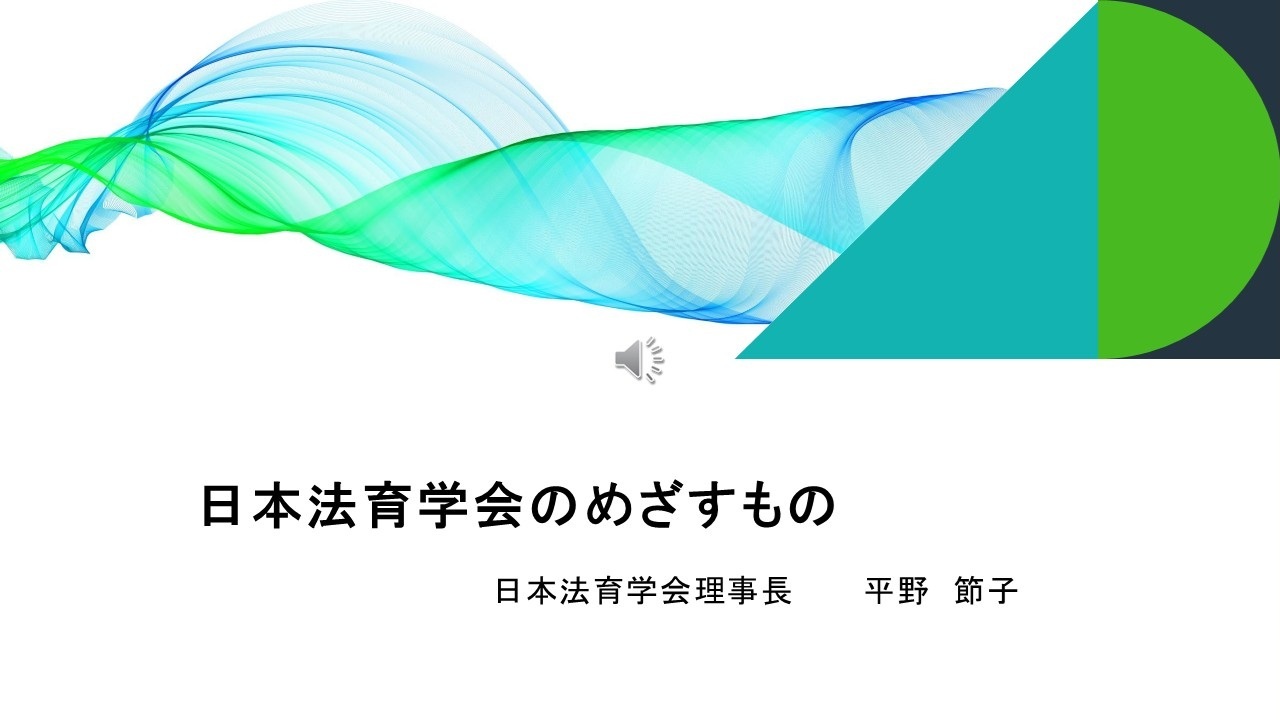
上記画像をクリックすると、理事長の音声つき「日本法育学会のめざすもの」のパワーポイントが開きます。
(2024年11月9日(土)収録)
「第7回全国研究大会 ご報告」
 令和6年(2024年)10月14日(月)日本法育学会と鹿児島司法精神医学研究会と志學館大学との合同研究大会を実施いたしました。
令和6年(2024年)10月14日(月)日本法育学会と鹿児島司法精神医学研究会と志學館大学との合同研究大会を実施いたしました。鹿児島大学医学部副医学部長の赤崎安昭先生に全面的協力を賜り、志學館大学のたくさんの先生方のご協力をいただき、桜島を見渡す素晴らしい40周年記念講堂で開催することができました。
今回の模擬裁判員裁判の題材は、2015年9月に実際にあった「熊谷6人殺害事件」です。被告人(ペルー人男性)の責任能力の有無が問われた事件です。既に結審しておりますが、新たに赤崎先生が鑑定書を作成してくださり、それに基づいて裁判員裁判と評議・評決を行いました。被告人の言動から、犯行当時心神喪失状態であったか、心神耗弱状態であったか、通常の判断能力があったかにより、有罪・無罪が分かれ、さらに、刑罰が大きく異なります。
最初に、赤崎先生に精神医学、精神鑑定についてご講義いただき、その後、会場から任意に参加された老若男女の裁判員による裁判員裁判が始まります。証人役である赤崎先生による緻密な鑑定書の内容から、裁判員の思考判断が大きく揺れ動いている様子が伝わってきました。
裁判員の評決は、実際の判決とは異なり、心神喪失と判断され「無罪」となりました。被害者にすればとても是認することはできない評決ですが、刑法39条1項により責任能力がないと判断した結果です。刑法39条1項は、行為の段階で、良し悪しがわからなかったり、自分を制御することができないときは責任を問わないということです。さらに、刑罰の意味がわからず効果も期待できない人に刑罰を科すよりも、精神科病院などに強制的に入院させて治療に専念することの方が犯罪を減らす、という観点からできた心神喪失医療観察法という法律が用いられます。
精神鑑定は非常に緻密で慎重に行われてアセスメントされ、鑑定書が作成されていました。そして、精神鑑定人はプロです。本当に統合失調症なのか詐病なのかはすぐに見抜くことができるそうです。被告人は、以前から「自分を殺そうとしている」人がいるという幻聴や幻覚がありました。
精神鑑定書や証拠・証言に基づき、最終的に判断するのは裁判員と裁判官です。感情に流されることなく、事件の背景を知り、事実を見極めた上で、自分の頭で考え、結論を出すことが重要です。
人生は、白とも黒ともつけがたいことに溢れています。決断することに迷い苦しむ機会がたくさんあることでしょう。模擬裁判員裁判は、事件という「素材」をもとに裁判という「形式」を用いて、自分の頭で精いっぱい考え、悩むこむことでご自分を成長させる訓練の場となるのです。そして大事なことは、他者の意見を聞いて、自分の見解を変えることがあってもよいということです。今回の評議の場面でも、最後まで迷っている様子が見られました。
鹿児島大会は、精神鑑定の難しさとその重要性を強く認識した貴重な時間となりました。また、模擬裁判員裁判は、参加者の主体的思考を大きく拡張する機会になることも再確認した次第です。
赤崎先生はじめご協力いただきました先生方、参加された皆様に心より感謝申し上げます。
令和6年10月25日
日本法育学会
理事長 平野 節子
「旧門司税関見学」


先日、旧門司税関を見学いたしました。
常に外国から人が行き来していた福岡県、山口県。日本人が知らない精緻な武器や薬物、高度な文化に脅威を感じつつ取り入れて、国を変革した若き獅子たちが闊歩する姿が目に浮かびます。
自由貿易を推進するも違法薬物などの侵入を防いだ税関の役割は大きいでしょう。
関門海峡では、今も大砲が日本海を睨んでいます。
令和6年1月21日
日本法育学会
理事長 平野 節子

「日本大学ダイバーシティシンポジウム」
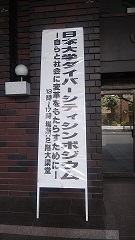

「日本大学ダイバーシティシンポジウム」は、他大学の取組みをはじめ、各学部長の姿勢、学生の取組みの発表等、とても充実した学びの機会となりました。4月28日に酒井学長を中心にダイバーシティ推進宣言がなされ、多様性社会における大学として船出したことをが明確化されました。今後は、女子学生、他国籍、障害者、LGBTQ+の方々にも大きく門戸が開かれた総合大学としての社会的責任が問われます。
とても長いこと日本のアカデミア、そして、日本大学の男性優位主義は継承されてきました。ご本人たちが気づかなくてもガラスの下駄を履き、ガラスのエスカレーターを登れるのが当たり前の男性たち。その陰で、たくさんの涙を流した人々がいることに思いをはせた男性はどれほどいるのでしょうか。変革に、理事長が女性、会合に女性を入れる程度の取組みだけでは、もう間に合いません。多角的アファーマティブアクションが必要です。そのためには、女性をはじめ多様な方々から意見・提案を行うこと。組織はそれを真摯に受け入れ、対策を練ることができる体制作りが必要です。
今回の講演会から、大学教育の中で、個々人の資質、バックグラウンドの違いを理解しようとする視点を醸成する機会を積極的に取り入れた教育課程を構築することが第一歩だと思いました。
令和5年7月2日
日本法育学会
理事長 平野 節子
映画「イチケイのカラス」
映画「イチケイのカラス」がいよいよ公開されました。竹野内豊さん演じる誠実に真実を追求しようとするちょっと変わった裁判官と手間がかかる捜査や手続きに不満を漏らしつつ誇りに感じている関係者たち。とても自分の中の正義感を揺さぶられる映画でした。
きっと作者は、「こうだったらいいのにな~」と現状の司法に一石を投じたかったのかも知れません。
先般お話しした木谷明先生をモデルにしている方は、小日向文世さん演じる裁判官でしょうか。
司法権の独立を謳いながら行政権に支配されている裁判官、正義を貫いて弱者を守るという志をもってせっかく司法界に入ったのに、真実を追及することは二の次で、上命下達に逆らえば出世できない構造に精神を病んでしまう裁判官・検察官も多いと聞きます。
本日、東電旧経営陣への無罪判決が出ました。どれだけ多くの人が唇をかみしめたことでしょう。責任は東電だけにないとしても、日本の司法はどちらを向いているのかしら、と思う冬の夕暮れです。
令和5年1月18日
日本法育学会
理事長 平野 節子
押田茂實先生『最終法医学講義』
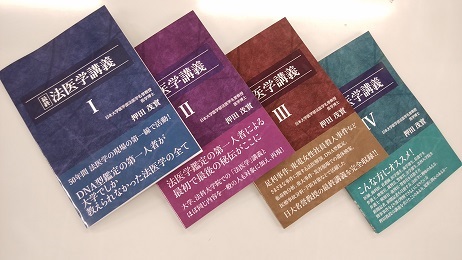
50年間法医学界で、DNA型鑑定の第一人者としてご活躍されました押田茂實先生が、この度、これまでの鑑定と実績の成果をまとめられた書籍を発刊されました。
『最終法医学講義』I~IVです。カラー版で具体的に事例が示され、とてもわかりやすくまとめられています。
DNA鑑定により、数々の真実を突き止め、冤罪を防いでこられた押田先生の熱意がひしひしと伝わってくる記録です。
法医学者だけでなく、法学者、薬学者、そして、裁判官にも手に取っていただきたい書籍です。
2022年4月17日
日本法育学会
理事長 平野 節子
新年度ご挨拶
皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。春の訪れと新たな出発に胸弾む時期ですが、ウクライナの人々の悲しみや苦しみを思うと、同じ地球に棲む人間として何ができるのかを日々考えております。
さて、日本法育学会は、COVID-19の拡大から学会としての活動を縮小し、約2年間は個別的な活動をして参りました。例えば、犯罪被害者支援や加害者支援、被虐待者相談受付や虐待関係研究、裁判傍聴等です。
新たな変異ウイルスの拡大も懸念されておりますが、今年度は、昨年度実現できなかった講演会や例年以上の社会貢献ができるよう努めたいと考えております。
ご指導ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2022年4月10日
日本法育学会
理事長 平野 節子
明けましておめでとうございます
皆様に幸多きことを心からお祈り申し上げます。日本法育学会は、人を見つめ、社会の在り方を考え、主体的に行動するための気づきを得る機会を提供したいと考えております。
昨年度は「虐待を防ぐために私たちにできること」と題して、虐待の根本にある問題、虐待被害から生み出される人生の歪みなど、一般書では決して知ることができない貴重なご講演、ご発表をいただきました。虐待は社会が破壊される一因であり、誰もが加害者・被害者になりうることを強く感じました。性的役割分業等のアンコンシャス・バイアス(unconscious bias)に気付くことがダイバーシティへの扉を開くことでしょう。多くの皆様に知っていただくために、来年度には書籍化する予定です。
また、今年度の締めくくりとして、虐待研究の第一人者の鈴木秀洋先生にご講演いただきます。詳細は、HPでご確認ください。
今後とも日本法育学会をどうぞよろしくお願い致します。
2022年1月1日
日本法育学会
理事長 平野 節子
「こころの時代」「イチケイのカラス」
9月12日㈰ 早朝5時から6時 NHK Eテレ 「こころの時代」 で、本会名誉理事である木谷明先生の生き方が紹介されます。皆様、録画してどうぞご覧下さい。また、木谷先生の被告人への公平な向き合い方を元にした刑事裁判官を主人公にしたドラマ「イチケイのカラス」。裁判官を竹野内豊さんが演じています。
ついに、「イチケイのカラス」の映画化が決定致しました。楽しみですね。こちらもお見逃しなく!
2021年9月5日
日本法育学会
理事長 平野 節子
裁判傍聴報告
社会を知る活動の一環として、8月3日に千代田区立麴町中学校の生徒47名を引率し、東京地方裁判所裁判傍聴を行いました。コロナ禍で傍聴席には少人数しか入れないので7班に分かれて、詐欺事件、暴行事件、覚せい剤事件等を傍聴しました。
傍聴終了後は、それぞれの事件についての内容と感想を話し合いました。生徒たちは初めての経験に、少し緊張している様子でしたが、もっと知りたい、調べたいという意欲を感じました。
2021年8月18日
日本法育学会
理事長 平野 節子
木村敬一さん
8月17日(火)午後7:30~8:42 サラメシ 真夏のSP!~東京2020の舞台裏だって働くオトナは腹がへる!~に、パラリンピック全盲の競泳メダリスト 木村敬一さんが出演しました。オンデマンドでご覧ください。
木村さんとは、渡邊淳先生のもとで演劇教育と法育について共に語り合いました。とても穏やかで懐の広さを感じさせる優秀な方ですよ。是非、応援よろしくお願い致します。
2021年8月18日
日本法育学会
理事長 平野 節子
「フォーラム90」を拝見して
「フォーラム90」の配信を拝見して、法育学会の価値を再確認しました。死刑は、国民を代表して刑務官が執行します。つまり、「国民全員が殺人をしているのと同じ」という木村草太氏の言葉が胸に刺さりました。また、青木理氏の取材から死刑制度の閉鎖性は国民を精神的負担から回避させていることにも気づきました。
つまり、本来責任ある立場の者たちが、一部の人の手が汚れるのを放置し、見ぬふりをして責任はとらない、という日本社会の無責任主義を露呈しています。
しかし、これまで日本の学校教育の中で、人権について考え、国民全員が殺人者になっていることを知る機会があったでしょうか。民主主義が成熟している国々では、日常生活や学校教育において人権について意識させる機会があり、個人に人権が存在することを前提に教員は指導し、議論されます。
1994年「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)に日本の批准が決まった時の教員たちの反発と戸惑いは凄まじいものでした。私は学校現場でその様子を目の当たりにし、「教員たちは、子どもに人権を認めたくないのだな」と思ったことを覚えています。
日本法育学会は、様々な社会の現場を見て体験して考えることを大切にしています。そして、自分も含め、社会についての無知に気づくのです。当事者意識、他者意識が重要なことはわかっています。でも、学校教育で社会の現状を肌で感じる機会が皆無に近い状態である今、まずは「知ること」こそ、思考停止から抜け出す一歩ではないでしょうか。「知ること」そして、「気づく」ことこそが、人間が人間であるための教育であると思っています。
10月23日(土)の開催の、第5回全国研究大会のテーマは「虐待を防ぐために私たちにできること」です。是非、子どもたちへの虐待の現状を知り、原因を探る必要性に気づいてほしいと思います。
2021年7月11日
日本法育学会
理事長 平野 節子
自立した市民の育成
日本法育学会は、「自立した市民の育成」を大きな目標として、模擬裁判員裁判の指導、裁判傍聴引率と解説、更生施設参観、講演会、研究会など様々な教育活動を行っております。法育研究会の時代を含めると、その活動は今年で25年になります。話題の千代田区立麴町中学校の模擬裁判員裁判指導は、その教育的価値を認められ、10年間継続しており、既に3年生の学校行事となっています。自立した市民には、「論理的思考力」「公平・公正な判断力」が求められます。それは、グローバル社会において最も重要な力の一つです。前提として、社会事象を多角的・批判的に見つめる見識が必要ですが、それは資質能力というよりも訓練によって誰もが身に付けられるものと考えています。議論をする機会を用意すれば良いのです。これまでの経験から見てみると、たった数回の指導で、子どもたちは学習や生活に意欲的になり、社会問題解決のために動き出すことが多いことからも察することができます。
近代社会になっても、日本人は予定調和を好み、強い同調圧力が蔓延る社会で生きているので、議論することを「争い」のように捉え、議論後の気持ちの切り替えが苦手です。それは単に議論することに慣れていないだけであって、議論場面や機会が増えることにより、表現の自由の価値を実感できると思います。大人の意識変革も必要でしょう。裁判という特別な場を設定することで、現実事象を現実から切り離して考えられ、裁判員という裁判を運営する立場で法律を学習しつつ、他者意識を有しながら老若男女が自由に主体的意見を述べられる機会を提供するのが模擬裁判員裁判です。
令和元年の研究大会では、司法への市民参加のもう一つの場である「模擬検察審査会」に挑戦しました。これほど実際に近い形での実践は、おそらく日本初ではないでしょうか。裁判員裁判と検察審査会は車の両輪に例えられます。しかし、発足以来60万人以上が検察審査会に参加しているにも拘わらず、その「非公開性」と「司法による価値の軽視」により、一般人は無知のままです。模擬裁判員裁判が、裁判員として裁判に参加するための知識獲得と主体的議論の練習となっているように、模擬検察審査会も同様の効果が期待されます。
2019年は、裁判員裁判が開始されて10年、検察審査会に法的拘束力が付与されてから10年という節目の年です。そこで、三井誠先生に検察審査会の歴史とその価値についてご講演いただき、模擬検察審査会を全公開方式で実施しました。午後のシンポジウムでは、元裁判官、元検察官、弁護士、研究者の先生方に、検察審査会の現状と今後について議論していただきました。終了後、多くの方々からの、「この素晴らしい制度を広め、活性化すべき」との声が印象的でした。
当日の様子を含め三井先生のご講演、検察審査会制度と裁判員制度の相違等は、『日本法育研究第4号』に掲載されています。
令和2年(2020年)の研究大会は、「虐待を防ぐために」と題しまして、戒能民江先生の基調講演をはじめ実践家のシンポジウムを予定しておりましたが、COVID-19の感染拡大により中止とさせていただきました。今年も、対面形式での大会開催は難しいかも知れませんが、実行方法を工夫し実施したいと考えております。これからも日本法育学会は、研究と実践を進めて参ります。
皆様、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
日本法育学会
理事長 平野 節子
日本法育学会
日本法育学会事務局
〒270-1196
千葉県我孫子市久寺家451
中央学院大学法学部
大久保輝研究室内
MAIL
info@nihon-houiku.jp
ゆうちょ銀行口座
口座記号番号 00160-8-587494
加入者名 日本法育学会